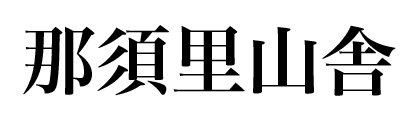92歳の知識人ノーム・チョムスキーと、グリーンニューディール研究の世界的第一人者ロバート・ポーリンが、気候危機解決の道を語った『気候危機とグローバル・グリーンニューディール』。Fridays For Future Japanによる日本語版まえがき、そして飯田哲也・井上純一・宮台真司各氏による力強い推薦の言葉に後押しされつつ、ついに予約受付が始まった。本の完成を記念し、当ホームページでは12月をとおして特別コンテンツを無料公開していく。今回はその第一弾として、訳者あとがきを4回にわたって掲載する。
Part 1: 気候危機は解決できる
気候危機は解決できる―本書のテーゼを一言で要約するとしたらこうなるだろう。責任ある政策議論をするためには、既存の枠組みと時間制限の範囲内で実施可能な政策を提案し、それを実施してから問題の解決に至るまでの経路を明確にしなければならない。ノーム・チョムスキーとロバート・ポーリンの『気候危機とグローバル・グリーンニューディール』では、まさにこのような議論がなされている。一般読者にも十分に伝わるような文体で書かれた作品だが、さらに議論をわかりやすくするために、邦訳では人物名や専門用語にすべて訳注による簡単な解説を追加した。グローバル・グリーンニューディール構想の概要はすでに本書中でうまくまとめられているため、ここではこの構想をより広い文脈に置いて考えてみたい。
まず「グローバル・グリーンニューディール」という概念は特に新しいものではないという点を確認しておこう。2008年金融危機からの世界経済復興計画の一環として、環境経済学者のエドワード・バービアは2009年2月に「グローバル・グリーンニューディール」と題された報告を国連環境計画(UNEP)技術・産業・経済局に向けて行った。これを受けてUNEPは、国際諸機関からの意見を参考にしつつ同年3月に『グローバル・グリーンニューディール―政策概要[1]』という報告書を発表した。さらにバービアは4月に長編報告書『経済復興の再考―グローバル・グリーンニューディール』を発表し、翌年の2010年にはこれを拡張した書籍として『グローバル・グリーンニューディール―経済復興の再考[2]』を出版した。一連の著作物においてバービアは、従来型の経済刺激策では金融危機からの復興は「茶色の経済」を再び実現してしまうだけであり、気候危機を解決するためには「緑の経済」への移行資金として多額の脱炭素投資が戦略的に行われる必要があると説いた(ちなみに2009年の時点でバービアとUNEPが「気候危機」という言葉をすでに使っていたという事実は特筆に価する)。こうした問題意識に基づいて、2009年グローバル・グリーンニューディール構想には世界規模の炭素市場の設立、化石燃料への助成金の廃止、そして世界GDPの1%の脱炭素投資などの政策案が含まれていた。ポーリンが顧問を務めた2009年アメリカ復興・再投資法のグリーン投資部門は、UNEPのグローバル・グリーンニューディール構想の「GDPの1%」という規模に匹敵する財政出動だった。その他にも国内GDP比で日本が1%、中国が3%、そして韓国が5%のグリーンニューディール投資をそれぞれ2009年に行った[3](その後韓国の実質的な脱炭素投資の金額は当初の約束の約半分へと下方修正されている[4])。欧州連合は同時期にGDPのたった0.2%しか脱炭素投資に当てておらず、他地域に比べ遅れをとっていた。バービアは、こうした財政出動は主に各国の国内経済の復興に向けられていたと指摘し、G20加盟諸国を批判して次のように書いている。
G20諸国の最大の失敗は、世界の貧困層の経済的・環境的脆弱性への配慮の欠如である。2008年~2009年の不況に先立って起こった食料危機や燃料危機によって、世界の貧困層の生活水準を貧困線まで引き上げるためのコストには約380億ドルという金額が上乗せされてしまった。G20諸国の財政支出計画には、こうした状況を改善するための策が一切含まれていない[5]。
グローバル・グリーンニューディールをめぐる議論はその後金融危機からの復興という問題が落ち着くにつれて下火となったが、2018年の世界的な気候運動の盛り上がりを受けて2019年頃から再び活気づいてきている。以上の歴史的文脈を踏まえると、バービアの名前こそ本書には登場しないものの、チョムスキーとポーリンの議論はこのUNEP構想を拡張するものとして理解されるべきだと言えるだろう。
本稿執筆時点では、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による『第六次評価報告書』の第一作業部会報告書[6](通称WG1)が発表されている。WG1では気候変動に関する自然科学的根拠の最新の知見がまとめられている。それ以前の報告書と比べ、WG1では温暖化の人為性について「疑いの余地がない」というIPCC史上最も強い文言が用いられた。氷河の融解、上部海洋の温度の上昇および酸性化、海面上昇、熱波、そして干ばつと熱波の同時発生に対しても、人為的である可能性が「とても高い」(90%以上)「きわめて高い」(95%以上)「ほぼ確実」(99%以上)という評価がなされている。2019年現在の大気中のCO2濃度は過去約200万年間で最も高く、同年の地球平均気温も過去約2000年間で最も高い。さらに南極の氷床の融解や森林の立ち枯れなどの臨界点事象については、それが起こる可能性は低いものの、起こった場合の地球環境への影響は甚大であるため、リスク評価の一部として考慮するとされている。例えば、南極の氷床の融解が起こった場合は、海面が2100年までに最大1.5メートル、2300年までに15メートル以上上昇する可能性がある。たとえ世界が排出量実質ゼロを達成して地球の表層温度の上昇を食い止めたとしても、海面上昇など一部の現象はその後も数十年から数千年かけて続く可能性がきわめて高いとされている。また温暖化対策の効果に関しては、排出量の大幅削減などを速やかに実施した場合、20年以内にその効果が観測できる可能性がきわめて高く、21世紀の終わり頃になれば極端現象の大幅な防止が成果として観測できるだろうとされている。
IPCCがまとめた最新の自然科学研究の一部を紹介した。本書ではチョムスキーもポーリンもこの分野に関する自分の専門知識の不足を潔く認めている。これは気候危機に限らず専門的な議論と向き合う際には誰もが見習うべき謙虚な態度だ。しかしながら、WG1の政策立案者向け要約を読む限り、気候危機の解決には「文字通り組織立った人間生活の存続がかかっている」と述べるチョムスキーの言葉が決して誇張ではないことが理解できるだろう。
つづいて、気候危機に関する世論に目を向けてみよう。イェール大学は2021年に世界31カ国でフェイスブックのユーザー7万6382名を対象に国際世論調査[7]を実施した。その集計結果をまとめた『気候変動に関する国際世論』によると、どの国でも「気候変動は起こっている」という回答が多数派だったが、アメリカやオランダ、オーストラリアやドイツなどの先進諸国では「気候変動は人為的である」「気候変動について十分な情報を持っている」という回答が多数派だったのに対して、フィリピンやナイジェリア、マレーシアやインドネシアなどの低中所得諸国では「気候変動は人為的ではない」「気候変動についてもっと情報がほしい」という回答が多数派だった。政府は気候変動対策を優先的に行うべきかという質問に対しては、すべての国で「最優先すべき」「優先すべき」が多数派を占めたが、その割合はコスタリカやコロンビアなどのラテンアメリカ諸国が約90%だったのに対して、サウジアラビアやエジプトなどの中東諸国は50%台に留まった。日本に焦点を当てると、パリ協定への支持率は世界第2位(95%)であり、気候変動は起こっているという回答の割合も上位(91%)だったのに対して、気候活動に積極的に参加したいと答えた人の割合は世界最下位(29%)だった。興味深いことに、気候変動対策は経済成長を促進させるかどうかという質問に対して、「促進させる」よりも「低迷させる」と答えた人の方が多かった国はオランダ、チェコ、そして日本の3カ国のみだった。
日本の大衆メディアではよく若い世代の方が気候危機に対して関心が高い(または上の世代の人々はこの問題に対して関心が低い)という主張が散見されるが、これは単なる偏見だ。内閣府の世論調査[8]によると、日本国民の約88%は気候変動問題に対して「関心がある」と答えており、また脱炭素社会の実現に向けての二酸化炭素等の排出量削減についても「取り組みたい」と答えた国民の割合は約92%にのぼった。回答者の年齢別に見てみると、年齢が上がればあがるほど「関心がある」「取り組みたい」と答えた人の割合も大きくなった。ただし、具体的にどのような取り組みをしたいと考えているのかを尋ねられると、個人レベルでの消費行動の見直し(責任ある企業の商品の購入、電気自動車の利用、省エネ、節電、再エネ利用、公共交通機関の利用等)が回答の上位を独占しており、「地球温暖化への対策に取り組む団体・個人の応援・支援」は約12%で最下位となっていた。
以上から、日本国民の現在の意識としては、すべての世代が気候危機に対して高い関心を持っており、これの解決に向けた取り組みにも積極的だが、具体的に行動を起こすとなると市場における責任ある消費が強調されているという傾向がある。国際的に見ると、倫理的消費とは別の軸で「地球を救うための政治参加」をしたいと考えている人々は日本においてはまだ少数派だ。こうした世論の現状を念頭に置きつつ、グローバル・グリーンニューディールをさらに深く検討するための材料として、以下ではいくつかの切り口から議論を深めてみたい。
[1] United Nations Environment Programme [UNEP]. (2009). Global Green New Deal: Policy Brief.
[2] Barbier, E. B. (2010). A Global Green New Deal: Rethinking the Economic Recovery. New York: Cambridge University Press. (エドワード・バービア著『なぜグローバル・グリーン・ニューディールなのか―グリーンな世界経済へ向けて』赤石秀之&南部和香訳、新泉社、2013年)。なおUNEP報告書およびバービアの2010年著書においては、ポーリン他による2008年報告書『グリーン経済復興』が度々引用されている。Pollin, R., Garrett-Peltier, H., Heintz, J., & Scharber, H. (2008). Green Recovery: A Program to Create Good Jobs and Start Building a Low-Carbon Economy. Washington, D.C.: Center for American Progress.
[3] Barbier, E. B. (2010). How is the Global Green New Deal Going? Nature, 464(8), 832-833.
[4] Sonnenschein, J., & Mundaca, L. (2016). Decarbonization Under Green Growth Strategies?: The Case of South Korea. Journal of Cleaner Production, 123(1), 180-193.
[5] Barbier, E. B. (2010). p.833.
[6] Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. (2021). Summary for Policymakers. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Eds. Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pirani, A., et al. Cambridge University Press.
[7] Leiserowitz, A., Carman, J., Buttermore, N., et al. (2021). International Public Opinion on Climate Change. New Haven, CT: Yale Program on Climate Change Communication & Facebook Data for Good.
[8] 内閣府. (2021). 令和2年度 気候変動に関する世論調査. https://survey.gov-online.go.jp/r02/r02-kikohendo/index.html