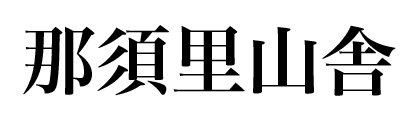92歳の知識人ノーム・チョムスキーと、グリーンニューディール研究の世界的第一人者ロバート・ポーリンが、気候危機解決の道を語った『気候危機とグローバル・グリーンニューディール』。Fridays For Future Japanによる日本語版まえがき、そして飯田哲也・井上純一・宮台真司各氏による力強い推薦の言葉に後押しされつつ、ついに予約受付が始まった。本の完成を記念し、当ホームページでは12月をとおして特別コンテンツを無料公開していく。今回はその第一弾として、訳者あとがきを4回にわたって掲載する。
Part 2: 『持続可能な開発レポート』という切り口
チョムスキーとポーリンが幾度も指摘しているとおり、気候危機の文脈で事業や政府がすべきことを考えるときには必ず国際的な気候正義の視点を議論に組み込む必要がある。国連が発表している年次報告書『持続可能な開発レポート[1]』はその文脈で大いに役立つ資料だ。そこで、ここでは同レポートの2021年版で取り上げられている論点のうち、グローバル・グリーンニューディールを実施するにあたって重要となり得るものをいくつか紹介したい。
まず、グローバル・グリーンニューディールへの資金源とパンデミック復興の財源論のつながりを確認しつつ、ここから見えてくる論点を整理してみたい。本書におけるポーリンの提案では、2050年までに排出量実質ゼロという目標を地球レベルで達成するために必要な資金は投資サイクルの初年度である2024年で約2.6兆ドルと見積もられている。このうち1.3兆ドルは公共部門からの出資となっているが、財源は「炭素税収」「軍事予算からの資金移転」「連邦準備制度および欧州中央銀行によるグリーン債購入」「化石燃料助成金の 25 %の再活用」の4項目から成る。どの項目においても先進諸国がその大半を賄うことが予想される。そのため、先進諸国から発展途上諸国へとグリーンニューディール資金が流れることになるわけだが、このような国際的なフローには必ずいくつかの問題が付随する。第一に、決済が行われる通貨が米ドルであるという問題。第二に、資金の提供や運用を行う主体間の力関係の問題。そして第三に、資金運用の成果の評価方法と汚職の防止に関する問題だ。この3つの問題は「グリーンニューディールの資金をいかに脱植民地的・ポスト帝国主義的な形で運用できるか」という課題としてまとめることもできる。
『持続可能な開発レポート』2021年版では、パンデミックからの復興のための財源論という文脈で以上のような問題点が整理されている。これはグリーンニューディールの財源論を考える上でも役に立つ議論だ。同報告書では、パンデミックからの復興のためには低中所得諸国の財政力を強化することが最優先課題であるとされている。では、低中所得諸国の財政力を決定している要因は何なのか。GDPに対する負債の割合が高いため政府が新たな融資を受けられなくなっているのだという通説があるが、同報告書はこれに対して、コロナ禍では先進諸国の方が低中所得諸国よりもGDPに対する負債の割合が高いにも関わらず、より多くの負債ベースの資金を調達し復興に当てることができたいう事実を指摘する。ここからは、GDPに対する負債の割合は一国の政府の資金調達能力を決定するわけではなく、むしろ負債の割合の高さと資金調達能力の高さの間には比例の関係すら見られるという結論が導かれる。同報告書には「全体として、発展途上諸国は負債を抱えすぎているのではなく、むしろ負債が少なすぎるのだ」という記述すらある。
より有力な説として、同報告書ではアメリカの連邦準備制度との「スワップライン」を持っているかどうかが各国の資金調達能力を決定しているという指摘がある。スワップラインとは、中央銀行が自国の通貨を米ドルと一定期間中に限度額付きで交換することを認める約定だ。パンデミック以前では、欧州中央銀行、スイス銀行、カナダ銀行、イングランド銀行、そして日本銀行がスワップラインを締結していた。パンデミック以後はオーストラリア、ブラジル、デンマーク、韓国、メキシコ、ニュージーランド、ノルウェー、シンガポール、そしてスウェーデンへ連邦準備制度は新たなスワップラインを提供している。スワップラインをもつ国は為替市場における自国通貨の価値を安定させやすくなり、よって自国通貨への信用格付けを高く保ち融資を受けやすくすることができる。その背景には、世界の外国為替市場の90%が米ドル建てで取引されており、世界の準備通貨においても2021年には米ドルが(下降傾向にあるとはいえ)59%を占め、世界の負債も米ドルが40%以上を占めているという状況がある。
この現状分析に基づいて、同報告書では以下の3つの解決策が提示されている。第一に、連邦準備制度がより多くの国々の中央銀行とスワップラインを締結すること。第二に、欧州中央銀行や日本銀行など国際的に取引されている諸通貨を扱う中央諸銀行もスワップラインを発展途上諸国の中央銀行に提供すること。第三に、国際通貨基金が低中所得諸国向けの特別引出権を大幅に拡張すること。融資以外の文脈で、『持続可能な開発レポート』は低中所得諸国における脱税問題を解決するために、主にロンドンやニューヨークの金融街のエリート税理士たちが首謀する様々な脱税を国際的に取り締まることも重要であると指摘している。また世界銀行を始めとする多国間開発諸銀行の融資力を大幅に増強する必要性も挙げられている。こうした策を講じることによって「低中所得諸国にも先進諸国と同等の財政力を確保する必要がある」。
『持続可能な開発レポート』のこうした議論をさらに広い歴史的文脈に位置づけてみよう。本書でチョムスキーも指摘しているように、アメリカは主にラテンアメリカ諸国や中東諸国への度重なる軍事介入や経済制裁を行ってきたという暴力的歴史をもっており、また国際法の遵守を一貫して拒むことで国際的な「アメリカ例外主義」の立場をとってきた。低中所得諸国がより大きな財政拡張を必要としているにも関わらず先進諸国よりも少ない融資しか受けられていない現状を理解するためには、アメリカのこの継続的かつ暴力的な抑圧を考慮に入れる必要がある。低中所得諸国に「先進国と同等の」財政の裁量が認められていない現状は、自然の摂理などではなく、米ドルの覇権を維持しつつ裕福な国々の人々へ他の国々の人々を従属させるために、アメリカ率いる先進諸国が意図的に構築し維持している体制だ。先進諸国による長期的介入と搾取によって低中所得諸国の人々は「ゆっくりとした暴力[2]」にさらされてきたが、そうした歴史にはスペクタクルとしての話題性がないため、当事者たちの声は様々な形で沈黙させられてきた[3]。
こうした文脈を踏まえつつ、本報告書のもう一つの重要な論点である「スピルオーバー」の議論へ移ろう。『持続可能な開発レポート』では4種類のスピルオーバー(国内における様々な活動や決定が他国に与える影響)が指標化されている。第一に、貿易に付随する環境的・社会的スピルオーバー。ここには諸外国の天然資源の使用や国内消費者の行動が諸外国の生産者に与える影響などが含まれる。第二に、国境を直接越える物質的フロー。ここには水質汚染や大気汚染などが含まれる。第三に、国際的な経済・金融フロー。ここには政府開発援助や不公平な税競争など、先述の財源論で取り上げた諸問題も含まれる。第四に、平和維持と安全保障のスピルオーバー。ここには兵器や武器の輸出入や国際的な組織犯罪などの悪い影響に加え、平和維持のための国際協力などの良い影響も含まれる。同レポートでは、高所得諸国およびOECD加盟諸国は総じて悪いスピルオーバーに偏っており、他の国々におけるSDGsの達成を妨げているという指摘がある。実際にSDG指標(SDGsの達成度を示す数字)と国際スピルオーバー指標とを比較してみると、SDGsの達成度が高い国ほどスピルオーバー指標が低い(すなわちスピルオーバーが悪性)という傾向が見て取れる。関連して、気候行動スコアの推移を見ると、傾向としてはどの所得層もほぼ横ばいを続けてきているが、国の所得が高くなればなるほど同スコアは低くなるという傾向も見て取れる。
また世界のコモンズへの各国の影響をより鮮明に可視化するために「グローバル・コモンズ・スチュワードシップ指標」の開発も進められている。国連SDSN、イェール大学、東京大学、そしてグローバル・コモンズセンターが共同執筆したプロトタイプ版レポート[4]では、計34個のインディケーターがエアロゾル、生物多様性、気候変動、陸地、海洋、そして水の6項目へ区分けされ、これがさらに「国内」「スピルオーバー」へと区分けされて指標化される見込みとなっている。いずれにしても、こうして見ると日本を含む先進諸国はSDG1(貧困撲滅)を始め自国民の暮らしの豊かさを向上する指標を高く保ちつつ、そこから生じる様々なコストや責任を低中所得諸国に背負わせているというおおまかな構図が浮き彫りになる。ただし、各所得層の内部では国ごとにスピルオーバーの善悪の度合いに大きな違いがあるため、法律や政策を整備すれば悪いスピルオーバーはかなりのところまで改善できるはずだとも『持続可能な開発レポート』では主張されている。
さらに同報告書はOECD加盟諸国における消費者の行動が地球環境に与えている悪影響にも言及しており、例えば食生活のエネルギー消費量と持続可能性の度合いを測る「栄養段階」インディケーターの悪さや肥満率の高さなどが指摘されている。食生活に関する議論を補足すると、戦後の世界における動物製品の消費量の急増は化石燃料の消費量の増加に比肩するほどの資源消費と環境負荷を引き起こしている。欧米諸国ほどではないものの、日本における肉の消費量も世界平均や東アジア平均より高く、1961年には国民一人当たりの供給量が年間7.63kgだったものが2017年には年間49.33kg(およそ6.5倍)にまで増えている[5]。動物農業(肉、乳、そして卵の生産)は世界の可住地の用途としてトップであり、可住地全体の約38.5%を占める(ちなみに他の用途は森林が37%、植物農業が12.5%、低木地が11%、川や湖が1%、そして都市およびインフラが1%となっている)。動物製品が世界のカロリー供給に占める割合は18%、たんぱく質供給に占める割合は37%となっており、栄養素の補給という面からも食料生産のための資源利用効率という面からもおそらく最も問題の多い産業であることがわかる[6]。また温室効果ガスの排出量においても、畜産業と養殖業は食料生産から生じる排出量の半分以上を占めており、世界全体のすべての産業部門からの排出量の13%以上を占めるという推計もある[7]。この値は自動車からの排出量の割合(約12%)とほぼ同等だ[8]。本書のグローバル・グリーンニューディール構想で畜牛農業がクローズアップされている背景にも以上のような事実がある。
[1] Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., et al. (2021). Sustainable Development Report 2021: The Decade of Action for the Sustainable Development Goals. Cambridge: Cambridge University Press.
[2] Nixon, R. (2011). Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge: Harvard University Press.
[3] Trouillot, M-R. (1995). Silencing the Past: Power and the Production of History. Boston: Beacon Press.
[4] SDSN, Yale Center for Environmental Law and Policy, & Center for Global Commons at the University of Tokyo. (2020). Pilot Global Commons Stewardship Index. Paris; New Haven, CT; & Tokyo.
[5] Ritchie, H., & Roser, M. (2017). Meat and Dairy Production. https://ourworldindata.org/meat-production#which-countries-eat-the-most-meat
[6] Ritchie, H., & Roser, M. (2013). Land Use. https://ourworldindata.org/land-use
[7] Ritchie, H. (2019). Food Production is Responsible for One-Quarter of the World’s Greenhouse Gas Emissions. https://ourworldindata.org/food-ghg-emissions
[8] Ritchie, H., & Roser, M. (2020). Emissions by Sector. https://ourworldindata.org/emissions-by-sector